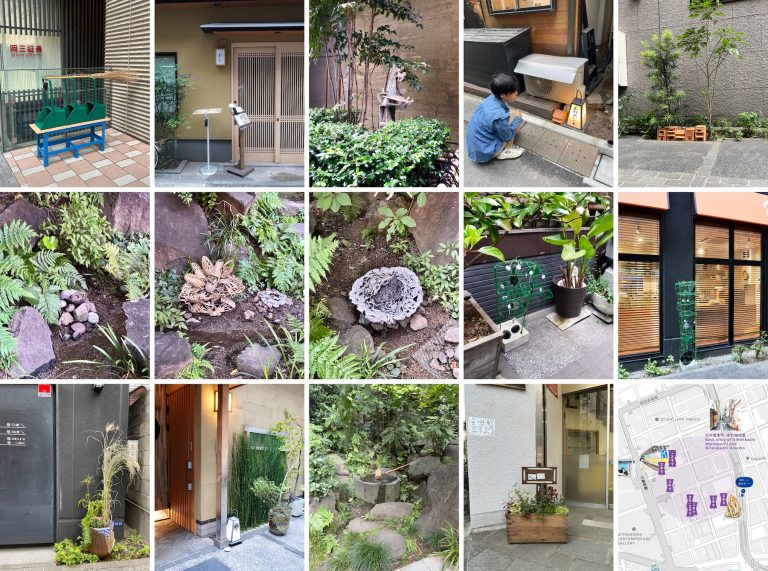
- 彫刻・立体
スキマプロジェクト/日本橋室町・本町

EVENTS
ワークショップ
会場
神田・秋葉原エリア
ものづくり館 by YKK
千代田区神田和泉町1-1 YKK和泉ビル
日程
10:30–11:30(受付開始10:00)
500円(付き添い保護者は無料)

怖い映画を見ている時、手で顔を覆ったその隙間からそ~ぉっと、のぞいたことはありませんか?指と指の隙間から見た世界は、少しだけ、いつもと違うような気がします。
指で作った窓から覗くと妖怪の本当の正体が見えた、という言い伝えもあるくらい、指と指の隙間には、実は、不思議な力があるらしいのです。
なので、この隙間に「ゆびのま」という名前をつけました。
床の間(とこのま)みたいに、ちょっと特別な空間です。
ゆびのま手袋は、指と指の間にファスナーが付いています。
自分の手なのに、ファスナーを開けると知らない空間が現れます。
床の間に掛け軸を飾るように、「ゆびのま」にも好きな絵を描きましょう。
「ゆびのま」は別の世界と繋がっているかもしれません。
「ゆびのま」には小さな生き物が住み着いているかもしれません。
対象者
針と糸が使える。玉結びと玉留めができる人。
小学生3年生以下は保護者との参加が必須です。
定員
10名(保護者参加可)
作り方
軍手の指と指の間にファスナーと絵を描いた布を、手縫いで縫い付ける。
工程
ファスナーを選ぶ/ファスナーを長さに切る/スライダー止めのため両端を縫う
フェルトを選ぶ/フェルトにペンで絵を描く/フェルトとファスナーを仮留め/布とファスナーを手袋に縫う
*完成品は持ち帰ることが出来ます。
【これが「ゆびの間」、YKKファスナーをひらいてびっくり!】



マップ
JR「秋葉原駅」より徒歩3分(昭和通り口)
東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」より徒歩2分(1番出口)

1981年東京生まれ。2006年 東京藝術大学院修士課程終了。身体と風景の関係を軸に、映像や立体、ドローイングなどを組み合わせた手法で作品を制作。最近は、伸びたり縮んだり、現れたり消えたりする、柔軟で交換可能な存在のあり方について考えている。個展に 「花と馬、会話」(Art Center Ongoing、東京、2024年)、参加展覧会に「瀬戸内国際芸術祭」(香川県粟島、2013・2016年)、など。
日本橋・馬喰町エリア
日本橋室町・本町の路地裏