
- トーク
Tokyo Perspective スペシャルトーク「写真の視線」

EXHIBITIONS

鈴木理策《日本橋室町から北側を見る》2025年
7組の写真家、アーティストが東京を歩き、「まちの今」を写真作品化。そのオリジナルプリントを特設会場(エトワール海渡リビング館)で展示するほか、ネット上のデジタルマップでも公開し、人々が撮影地点に訪れて実際の風景に対峙できるプロジェクトです。さらに、セブン-イレブン各店舗のマルチコピー機で手軽にプリントできる仕組みを用意し、新しい写真鑑賞やコレクションの楽しみ方を探ります(プリント方法は下記の説明を参照)。
協賛:富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
特別協力:株式会社エトワール海渡

《本郷菊坂界隈》
〈本郷菊坂界隈〉
電車に遅れまいと急いだり、スマホ片手にスーパーに向かったりしている時、僕たちは自分が「歩いている」ということを忘れて歩いている。周りのことも最小限しか見えていない。
いっぽうで、自分が「歩いている」ことが、よく意識される場合がある。脚が痛くなったとか道に迷ったとか、不測の原因によることが多いが、時にはそれに伴って「なんで歩いてるんだっけ?」とか「歩いてるって、どゆこと?」などという、普段とは異なる疑問が湧いてきたりもする。
「散歩」とはたんに歩くことではなく、そのような「歩いている」状態に、自らの身をあえて置くことである。散歩の魅力は「歩いている」状態がもたらす刻一刻の、知覚経験の豊富さの中にこそある。散歩のあいだ、目に映るものは分け隔てなく、しかも普段とは異なる説得力をもって迫ってくる。僕たちは現実空間の中を、現象学的と呼んでもよいくらいの濃密な知覚や身体意識と共に歩くのだ。まるで水の中を泳ぐようにして。

《Tokyo / Ueno #001》2025年、発色現像方式印画© Mari Katayama, courtesy of Mari Katayama Studio and Galerie Suzanne Tarasieve, Paris
〈Tokyo / Ueno〉
上野公園に立つと、進学して最初の授業で先生に投げかけられた問いと、そのときの緊張感を思い出します。「ここがどんな場所か知っていますか?」
人が生きる限り、歴史が作られていく。学生時代の私は道端の小石にさえ理由を探し求めるほど、あらゆる事象に説明を欲していました。だからなのか、いくら歩いても上野公園の道を覚えられることはなく、慣れないのです。
撮影には中判フィルムカメラを使っています。セルフポートレートを撮るときは長いレリ ーズでバルブ撮影を行いますが、シャッターを閉じるには手動でフィルムを巻き上げる必要があり、カメラのもとへ戻らなければなりません。その間に生じる時間差によって、私の身体は半透明に写ります。これはデジタル編集や多重露光の効果ではなく、物理的な撮影条件から生まれる現象です。透けた身体はコントロールできない景色や環境と一体化し、場所の模様として記録されます。
たまたま生まれた私たちが、人為的につくられた世界のなかで、どこまで調和を保てるのか、撮影のたびに考えます。人が作ったものは間違いに満ちています。
知らないこと、それから当然と思っていた価値観や基準を一度忘れ、改めて考え直すこと。上野公園での緊張は、私の撮影の原点なのかもしれません。

《red1》2025年(シリーズ〈URBAN RITUAL /Tokyo2025〉より)
〈URBAN RITUAL /Tokyo2025〉
東京は巨大都市(メガシティ)という形容が定着して久しい。「1000万都市」東京は1950年代にニューヨークを抜いて世界一となり、64年には2000万人を、85年に3000万人を突破、2020年にはついに4000万人を超えて世界一を突き進んでいるという。
行政区をまたいで延伸する都市圏は衛星画像からも確認できる。統計上の数字とはいえ驚くべきことだが、そこに住んでいる住民に「世界一」の実感があるのかどうかはわからない。人口密度が連続する集積地域(urban agglomeration)の内側は不均質な「地元」の積み重ねではないだろうか。
そんな「町」の一角を切り取りつなげて連続性のパターンを作ってみる。不均質な都市から取り出す地元文様の試み。今回は東京ビエンナーレが繰り広げられる神田川沿いの高低差を含んだ地形と、そこを通る動脈である電車をモチーフにした。庶民の遊び心が生んだ江戸小紋ではないけれど、メガシティならではの文様と言えるかもしれない。

《イエロー/東京藝大絵画棟7階研究室》
街を散歩していると、目に映し出される全ての風景を創りだしている制作者をイメージしてしまう。
「路上の石」があるとすると、アスファルトを敷き白線を引く道路工事者の行為の上に、誰かが運んできた石が路肩に息を潜めるようにじっとしている、と読み解く。ビル群のスキマに小さな一軒家を見ると、戦後の焼け野原に木造建築を建てた棟梁達の技術や考え方と、型枠にコンクリートを流し込んでビルを建てる建築のサスティナビリティを比較するように見てしまう。
私は、行為の連続性から創造される「部分と全体」の因果関係を、作品やプロジェクトを通して表現してきた。釘一本の意思と、東京という都市の意思。部分を創り出す創造力と、都市を構成する全体の創造力は、人間社会や地球環境にいかなる関係を築いているのか? その関係項に私がひとつの行為を加える事で、部分と全体の関係は、どのように変化するのか?
今回の写真制作においては、風景を構成する部分と全体の関係をひとつの表現体として捉えている。そしてその表現体を見つめる私の視線を黄色いボールに置き換え、風景全体に新たな部分として介入する試みである。
*室内から撮影した場所が3か所あります。その場所に入るためのルールは、ウェブサイトやマップに記載します。

《INVISIBLE PEOPLE》2025年(シリーズ〈underpass poem〉より)
〈underpass poem〉
昔、神田に住んでいました。よく散歩をしていましたが、気になるけれどあえて立ち止まって見ることがなかった場所があります。それが首都高上野1号線の高架下です。
首都高1号羽田線の歴史は古く、高架下のガードレールや柱に排気ガスのススが長年降り積もって、真っ黒になっています。最近の車はそんなに多くの排気ガスを排出しないので、今となってはただ汚い高架下に歴史を感じてしまいます。また場所によっては誰かが指で書いた落書きがちらほらと点在していて、渋滞時よくそれを眺めていました。
意味不明な落書きが多いのですが、よく見れば中央分離帯など人が歩かない場所にかかれているものもあり、意外な作為性があります。今回、久しぶりに神田を訪れて散歩をしたとき、私たちもススを指で拭って詩を描いてみました。一見簡単そうに見えるのですが降り積もったススが固まっていて、一本の線を引くことすら難しく、手も服も真っ黒になりました。触れてみて初めてわかる街の姿があるのだと思います。もし、場所を探しに散歩してもらえるのであれば、皆さんもぜび触ってみてください。

《日本橋室町・東を望む》2025年
〈解像度について〉
東京の写真は東京生まれの人が撮ったものが面白い、と学生の頃に聞いたことがある。変わってしまった風景に撮影者が思い出を投影するからだろうか。他所で生まれた人よりもシャッターを押す理由が多くあるということなのか。
写真の作業を「撮影」と「撮影の後で撮った写真を見ること」に分けて考えてみる。出来上がった写真を見る時、そこに撮った理由が表れていると、撮影者の思い出や感情を想像し、気持ちを重ねることができる。写真は、実際にシャッターを押した時に生まれるのではなく、もっと遡った時間、撮影者の過去の経験や記憶から生まれる場合も多い。複層的な時間をそなえていることは写真の魅力のひとつだと思う。
では撮られた写真からは何が生まれるか? そこから始めることはできないかと考えた。対象とカメラの距離が写真の種類を決定することは経験上心得ている。だが手法が導く効果の道すじから離れて、東京を撮影してみたいと考えた。

〈Backshift 2025〉シリーズより
〈Backshift 2025〉
東京ビエンナーレ2025の開催エリアには、過去に私が個展をした場所が複数含まれている。「犯人は現場に戻る」という俗説に沿うかのような、あるいは帰巣本能に促されるような気持ちで、しばらく行くことがなかったその場所を訪ねてみる。
かつて短期間だったが自分の作品を置いた記憶は鮮明で、まだその時のストレスは続いている。当時は作品を展示する空間になるべく、壁を塗り、照明に苦心した小さな経験の場だったが、今は建物や土地という不動産としての別の相がみえる。いつその場と関わったかということ、そして今回もその場を見にいったということ。この空間に個人的に関わる2点の事実を、時間軸を通して文章のように結びつけるために撮影という方法を選んだ。
建物は35年前と変わらずにある場合もあれば、すでに取り壊されて駐車場になっている場合もある。共通していたのは、当時の関係者は現在その住所にはいないということである。
全国のセブン-イレブンに設置されたマルチコピー機で、このプロジェクトの作品をプリントできます。世界で活躍する写真家たちが東京をとらえた作品を気軽に入手できるまたとない機会を、ぜひお楽しみください(2L版=12.7×17.8cm/フォト用紙/1枚600円)。

Step 1. 下記のウェブページから写真を選びます。
東京の地場に発する国際芸術祭「東京ビエンナーレ2025」TOKYO PERSPECTIVE
Step 2. 選んだ写真のプリント予約番号(例:TBP10001)を控えセブン-イレブンへ。
Step 3. 店内のマルチコピー機でプリントします。
① タッチパネルのメニューで「プリント」→「ネットプリント」を選択。
② 8桁のプリント予約番号を入力し、「確認」を押す。
③ 写真のプレビューを確認し、間違いなければ「これで決定」を押す。
④ お支払いは「コインでお支払い」か「nanacoでお支払い」を選べます。
・コインでお支払い:硬貨を投入
・nanacoでお支払い:電子マネー(nanaco)でのお支払い
⑤ 「プリントスタート」を押す。プリントが始まります。
⑥ 「終了」ボタンで終了(領収書の希望時は案内に従う)。プリント、おつりやnanacoカードのお取り忘れにご注意ください。
マップ
JR総武線「馬喰町駅」4番出口より徒歩2分
都営新宿線「馬喰横山駅」A1出口より徒歩6分

写真家。1958年岩手県陸前高田市生まれ。東京を拠点に自然・都市・写真のかかわり合いに主眼をおいた作品を制作。2001年ヴェネツィア・ビエンナーレに日本代表の一人として出品。2012年ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展日本館に出品(金獅子賞)。2001年第42回毎日芸術賞。2012年芸術選奨文部科学大臣賞。日本芸術院会員。
日本橋・馬喰町エリア
エトワール海渡リビング館

1987年、埼玉生まれ、群馬県育ち。2012年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。片山の活動の核心は、自身の身体の中で日々を生きることであり、その身体を生きた彫刻、マネキン、そして社会を映し出すレンズとして使っている。手縫い・手作りのオブジェと写真の組み合わせは「自然、人工、正しさ」といった社会の規範的な考えを映し出し、それに挑戦する作品を作り続けている。
また、2011年より「ハイヒール・プロジェクト」を主催し、身体能力に関わらず全ての人が「選択の自由」と持つことと、「選択する最前提条件としての選択肢」を用意することを目指す。アーティストに留まらず歌手、モデル、講演者としてもステージに立ち、活動し続けている。
日本橋・馬喰町エリア
エトワール海渡リビング館
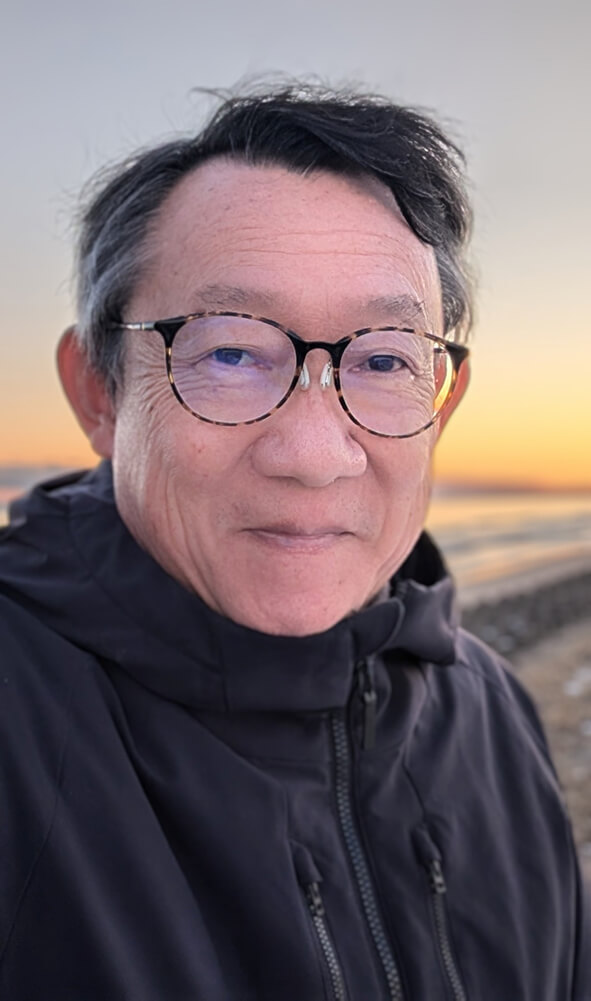
写真家。多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所所長 イメージの発生と記憶などをテーマに広範な活動をつづけている。あいちトリエンナーレ2016芸術監督、台湾最大の芸術祭「台3線芸術祭」2023では国際キュレーターを務めた。『風景論ー変貌する地球と日本の記憶』(中央公論新社)で2019年度日本写真協会賞受賞。近著に『写真論――距離・他者・歴史』(中央公論新社、2022年)、『ヒルマ・アフ・クリント 色彩のスピリチュアリティ』(インスクリプト、2025年)など。
日本橋・馬喰町エリア
エトワール海渡リビング館

アーティスト/東京藝術大学美術学部教授
芸術未来研究場 アート×ビジネス領域長
1963年秋田県大館市生まれ。1993年「The Ginburart」(銀座)、1994年の「新宿少年アート」(歌舞伎町)でのゲリラ型ストリートアート展。秋葉原電気街を舞台に行なわれた国際ビデオアート展「秋葉原TV」(1999〜2000)、「ヒミング」(富山県氷見市)(2004〜2016年)、「ゼロダテ」(秋田県大館市)(2007〜2019年)など、地域コミュニティの新しい場をつくり出すアートプロジェクトを多数展開。1997年よりアート活動集団「コマンドN」を主宰。
2010年民設民営の文化施設「アーツ千代田 3331」(東京都千代田区)(2010〜2023年3月閉館)を創設。地域に開かれたアートセンターとして、約13年間運営を行う。2001年第49回ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館に出品。マクドナルド社のCIを使ったインスタレーション作品が世界的注目を集める。2020年より「東京ビエンナーレ」の総合ディレクターを務める。著書に『美術と教育』(1997)、写真集『明るい絶望』(2015)、『新しいページを開け!』(2017)、『アートプロジェクト文化資本論:3331から東京ビエンナーレへ』(2021)。平成22年度芸術選奨受賞。2018年日本建築学会文化賞受賞。
日本橋・馬喰町エリア
エトワール海渡リビング館

撮影:濱田晋
2012 年より活動を開始。メンバーは高須咲恵、松下徹、西広太志。映像ディレクターとして播本和宜が参加。「風景のノイズ」をテーマに、路上を舞台とした作品制作・発表を行うことを活動の主とし、ストリートカルチャーに関わる多様なアーティスト達と共同したプログラムを行っている。
日本橋・馬喰町エリア
エトワール海渡リビング館

写真家。1963年、和歌山県新宮市生まれ。1998年、地理的移動と時間的推移の可視化を主題にシークエンスで構成した初の写真集 『KUMANO』 を出版し、2000年『PILES OF TIME』で第25回木村伊兵衛写真賞を受賞。ライフワークともいえる熊野での撮影の他、南仏のサント・ヴィクトワール山、セザンヌのアトリエ、桜、雪のシリーズといった多様な対象を異なるアプローチでとらえているが、一貫しているのは「見ること」への問題意識と、写真というメディア の特性への関心である。
主な展覧会に「絵画と写真 柴田敏雄と鈴木理策」(アーティゾン美術館、東京、2022年)、「意識の流れ」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川/東京オペラシティアートギャラリー/田辺市立美術館、和歌山、2015–2016)、「水鏡」(熊野古道なかへち美術館、和歌山、2016年)、 「熊野、雪、桜」 (東京都写真美術館、2007年)など。
日本橋・馬喰町エリア
エトワール海渡リビング館

1967年埼玉県生まれ。1993年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修士課程修了。日常社会の制度や仕組みを批評的に捉え、人間の思考の「型」を見出すことをテーマとしている。近年の個展に、「発生法──天地左右の裏表」(東京都現代美術館、2023年)、「資本空間 スリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸vol.1」(ギャラリーαM、東京、2015年)が、またグループ展に「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」(国立新美術館、東京、2019年)がある。
日本橋・馬喰町エリア
エトワール海渡リビング館