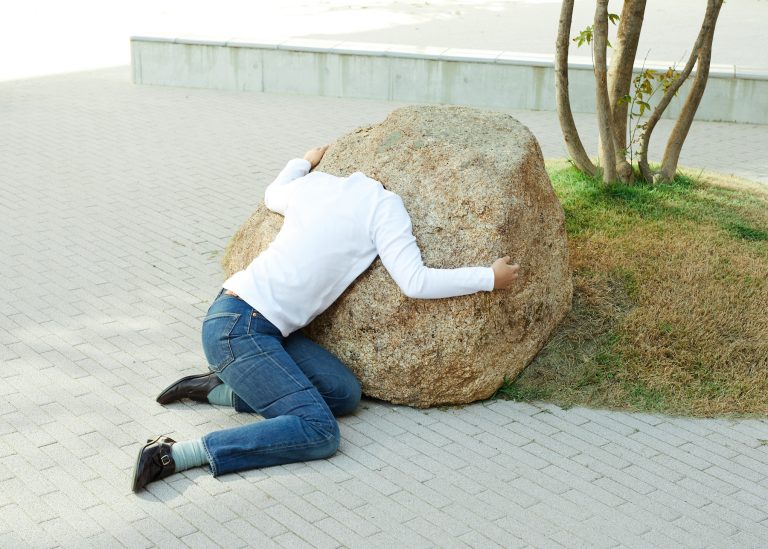- 彫刻・立体
藤原信幸:ガラスを使って自然を表現する「植物のかたち」2025
藤原信幸は「いきもの」のかたちに魅力を探り、これらをモチーフとして繊細かつダイナミックなガラス造形作品を生み出します。彼のガラスへの関心は、光がもつ環境に与える力を感じとり、光がつくる空間の可能性を追求することにつながっています。その長いキャリアを通じて、彼はガラス表現の可能性をめぐる探求と葛藤を繰り返しながら、これらを象徴的な「かたち」に変換しようと試みています。
今回はその実践から生まれた作品群が、寛永寺の空間と呼応するように展示されます。2009年頃から制作を始めた〈小文間の植物シリーズ〉は、自身の工房がある茨城県取手市、利根川流域の小文間(おもんま)に自生する植物の生命力に触発された作品群です。自然の中にある生命サイクルを身近に感じながら、植物の断片的なイメージを独自に組み合わせて再構築したものです。これらが創建400年を迎える寛永寺で再構成され、新たな空間イメージを創出します。
特別協力:東叡山 寛永寺
協 力:東京藝術大学
【開催前】2025.10.17 - 12.14 / 東叡山 寛永寺 貴賓室